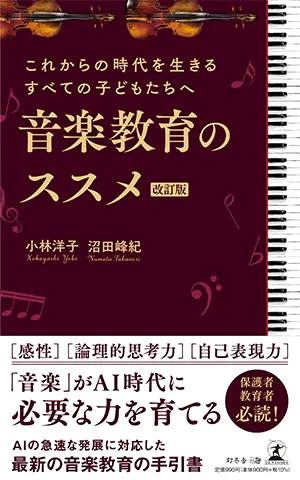相対音感とは?基礎知識と鍛え方
相対音感とはどんな能力か
「絶対音感」という言葉はよく知られていますが、「相対音感」という言葉にはあまり馴染みがない方もいるかもしれません。
相対音感(英: Relative Pitch)とは、基準となる音を聞いたうえで、他の音の高さを正しく判断できる能力を指します。
たとえば、単独で鳴った音の音名を当てるのは難しくても、続けて鳴らされた音と比べて「高い」「低い」「何度の間隔がある」などを判断できる場合、その人には相対音感が備わっているといえます。
人間は本来、相対音感を生まれつき持っているといわれています。ただ、日常生活の中では意識的に使うことが少ないため、その力に気づかずに過ごしたり、使わずに衰えてしまうこともあります。一方で、訓練を積むことでいつからでも高められる能力です。絶対音感が幼児期の訓練を必要とするのに対し、相対音感は年齢に関わらず伸ばすことができます。
相対音感を鍛えるメリット
相対音感を育てることで、音楽をより深く楽しめるようになります。
音の高さだけでなく、和音や旋律の進行、複数の音の関係性を瞬時に把握できるようになり、楽譜を読む力や暗譜も向上します。
また、高度な相対音感が身についてくると、耳で聴いた音楽をそのまま歌ったり楽器で再現したりする「耳コピ」も可能になっていきます。
楽譜が手元になくても演奏や歌唱ができるようになるのは、大きな楽しみや自信につながります。

相対音感レッスン
相対音感を伸ばすための方法
相対音感は子どもから大人まで、誰でも訓練によって育てることができます。特にソルフェージュ(視唱・聴音など)を繰り返し行うことが効果的です。
たとえば、音楽大学や専門学校では入試に聴音試験が課されることがあります。主音や和音など基準となる音を提示され、それに基づいてメロディーを書き取る課題が多いのは、相対音感を前提にしているためです。
日本の学校教育では、移動ド唱法を用いて相対音感を育む指導が行われています。
移動ド唱法では、曲の調に応じて「ド」の位置が変わります(例:ハ長調ではCがド、ト長調ではGがド)。これにより相対的な高さの感覚が養われます。一方、音楽の専門教育では固定ド唱法が採用されることが多く、どの調でも同じ音に同じ音名を割り当てるため、基準音を認識しながら相対音感を磨くことができます。
聴音や視唱の練習では、最初にピアノなどで基準音を確認してから取り組むことが大切です。地道な訓練を続けることで、聴き取ったメロディーを楽譜に書き起こす力も自然に育っていきます。
ピアノで実践的に相対音感を身につける
相対音感をより実践的に鍛えたい方には、ピアノの学習がおすすめです。
ピアノは平均律で正確に調律されており、鍵盤上で音の高低を視覚的に確認できます。自分で音程を作る必要がないため、演奏を通じて自然に相対的な高さを学べます。また、鍵盤の並びによって音の関係を目で見ながら把握できることも大きな利点です。
多くの音楽大学では、専攻を問わず副科ピアノを必修としています。これは相対音感だけでなく、和声感覚やアンサンブル力、音楽的な基礎を総合的に育む上でピアノが最適な楽器だからです。
特に効果的な練習としては、24のすべての調でのスケール(音階)とアルペジオ(分散和音)を習得することが挙げられます。これはピアノの技術を高めると同時に、調性と相対的な音程感覚を養うために欠かせない訓練です。
相対音感を伸ばし、音楽をもっと楽しむ
相対音感は特別な才能ではなく、誰にでも備わっている能力です。練習を積めば年齢に関わらず向上し、音楽の楽しみがさらに広がります。
「耳で聴いた音を正確に理解できるようになりたい」「楽譜をもっとスムーズに読めるようになりたい」と思ったら、相対音感のトレーニングを始めてみてはいかがでしょうか。

ピアノレッスン
当教室主宰の著書「音楽教育のススメ(幻冬舎)」