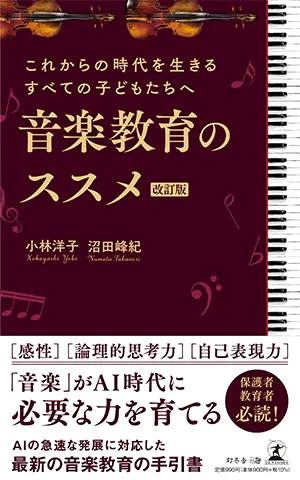聴音とは? 特徴と効果的な練習法を解説
音楽を深く理解し、表現豊かに演奏するために欠かせない「聴音」。
この記事では、聴音の基礎知識、ソルフェージュとの関係、試験対策、効果的な練習法について、専門的な視点から解説します。

聴音とは? ~音を「楽譜に戻す」力
聴音とは、耳で聴いた音を五線譜に書き取る力を養う訓練です。「演奏」が楽譜を見て音にする行為であるのに対し、「聴音」は音を聴いて楽譜にするという、逆方向の知的作業と言えます。
音を正確に記譜するには、拍子・音程・音価(音の長さ)などの複合的な要素を、瞬時に聴き分けて書き留める必要があります。この力を養うことで、実際の音と楽譜との関係性を深く理解し、演奏力や読譜力の基盤を築くことができます。
聴音には主に次の2種類があります。
「旋律聴音」:ピアノなどの単旋律・複旋律を聴いて書き取る
「和声聴音」:同時に鳴る複数音(和音)を聴き取る
ソルフェージュとの関係
聴音は、音楽教育における「ソルフェージュ(solfège)」の一分野です。ソルフェージュとは、音楽の基礎を総合的に養う教育メソッドで、以下のような力を育みます。
・楽譜を正確に理解して演奏できる力
・表現力の豊かな演奏を支える感性と知識
・読譜の速度向上による演奏効率の向上
こうした効果を持つにもかかわらず、日本ではソルフェージュが初歩的な補助学習と見なされ、省略されがちです。一方で、欧米では初心者から専門家に至るまで、音楽理解と演奏の基盤としてソルフェージュを継続的に学ぶことが常識とされています。
聴音を含むソルフェージュは、単なる「音感トレーニング」ではなく、音楽の構造を「読む力」と「聴く力」を統合的に育てるための学習です。

聴音レッスン
試験対策 ~基本ルールと準備のコツ
音楽大学の入試等の試験では、聴音は以下のような流れで実施されるのが一般的です。
①事前情報の提示
音部記号・拍子・小節数・調性などがあらかじめ示されます。
②基準の提示
テンポ(メトロノーム音)や基準音(A音、主音、主和音など)が演奏前に提示されます。
③再生回数
課題は2~3回、通奏(全体再生)や分奏(前半・後半分けて再生)で流されます。
この形式は、絶対音感がなくても対応できる構成になっており、適切な準備と訓練を重ねれば誰でも習得可能です。
準備のためのポイント
・2B以上の柔らかい鉛筆を使用(視認性・筆記のしやすさを重視)
・消しゴムを極力使わず、集中力を保って記譜する練習を
・小節の枠を意識し、拍ごとの空間設計を整える記譜習慣を身につけましょう
減点されやすいミスとその対策
以下は、試験で減点されがちなポイントとその対策例です。
①白紙・未記入
自信がなくても書く姿勢が大切。部分点を狙いにいく意識を。
②記号の誤用や記譜の乱れ
臨時記号(♯、♭、♮)や調号の順番など、基本的な書き方を見直す。
③拍子との不一致
拍数に合わない音数・リズムになっていないか、全体のバランスを確認。
④複旋律のズレ
上下段で拍が揃っているかを意識。縦の一致に注意。
効果的な練習方法 〜 音楽的構造を意識して取り組む
聴音力は、単なる「音当てゲーム」ではなく、音楽的な構造と予測を伴った「知的な聴取」によって高まります。日々の練習では、次のような視点を取り入れることで、より本質的な力を養うことができます。
■ 基礎力を養う日々の習慣
①1日1題の練習を継続
拍子感・リズム感を含む基本的な耳の精度を鍛えます。
②録音→自己採点→誤答分析
何を間違えたか、なぜ間違えたかを明確にする習慣を持つことで、学習効率が飛躍的に向上します。
■ 音楽構造を踏まえた「予測的な聴取力」の養成
①調性の正確な把握
調号・終止形を意識することで、臨時記号の予測と判断が容易になります。
②和声の流れを意識する
I–IV–V–Iなどの典型的な和声進行に親しむことで、次に来る音の予測が可能になります。
③モチーフの反復や変化を捉える
旋律の中で繰り返される音型を把握することで、記憶と再構成が容易になり、構造的に整理された聴き取りが実現します。
④記譜の視覚的整合性を高める
拍の配置、小節内のバランスなど、見やすく正確な楽譜を書くことも試験での評価対象になります。
予測と文脈理解が「音楽的な耳」を育てる
音楽は文脈をもった芸術です。単に聴いて写すのではなく、「次に何が来るか」を予測しながら聴くことは、作曲家の意図を理解し、演奏につなげる力へと直結します。
音楽的文法を理解し、予測と検証を繰り返すことで、記譜だけでなく表現や解釈の力まで育つ——それが聴音の本質的な価値です。
まとめ
聴音は、音楽教育の根幹をなす重要な訓練です。「聴く力」と「書く力」のバランスを養うことで、楽譜を正確に理解し、音楽の本質に迫る力が身につきます。
一見地味に見える学習かもしれませんが、その積み重ねこそが、音楽家としての深い耳と確かな演奏力を支える土台となります。焦らず、毎日の練習の中で「音楽を聴く耳」を育てていきましょう。
当教室主宰の著書「音楽教育のススメ(幻冬舎)」