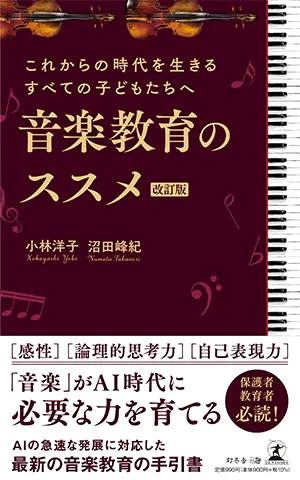良い声を出すために必要な食事と飲み物
〜発声を支える、喉にやさしい日常習慣~
美しく響く声を出すためには、正しい発声練習だけでなく、喉のコンディションを整える生活習慣が欠かせません。声帯は非常に繊細な器官であり、わずかな乾燥や炎症、疲労によって声が出にくくなったり、音域が狭くなったりすることがあります。
本記事では、喉に優しい飲み物や食事、避けるべきものや摂取の工夫、そして日常でできる声のケア習慣について、音楽教育や歌唱の観点から解説します。
声帯を整えることは、歌の上達への第一歩
歌が上手くなるためには、無理な練習よりも質の高いトレーニングと、喉を整える生活習慣が大切です。特に、以下のような習慣が声帯に悪影響を与えることがあります:
・寝不足やストレスによる粘膜の乾燥
・空気の乾燥・埃の吸引
・強く咳をする・大声を急に出す
・冷暖房による湿度の低下
・食事や飲み物による喉の刺激
発声の質や音域、持久力を高めるには、声帯周辺の環境を守ることが不可欠です。

声楽レッスンはこちら
喉に優しい飲み物とは?
■避けるべき・摂り方に注意したいもの
①冷たい飲み物
声帯周辺の筋肉を収縮させ、発声の可動域を制限する可能性があります。練習・本番前は常温が基本。
②熱すぎる飲み物
粘膜を刺激しすぎたり、逆に乾燥を引き起こすことがあります。
③コーヒー・紅茶(カフェイン)
利尿作用により体内の水分が奪われやすく、喉の乾燥を招きます。摂るなら水分補給も併用。
④ウーロン茶
脂質分解作用が強く、喉の潤いを保つ油分を洗い流してしまうことがあります。
⑤アルコール・ビール類
一時的に気分が高揚し歌いやすく感じても、脱水作用や粘膜への刺激が強いため、本番前は避けましょう。
⑥炭酸飲料
炭酸の刺激やゲップによる腹圧低下により、発声しにくくなります。
■おすすめの飲み物
①常温の水
最も基本で安全な選択。こまめな水分補給で喉の粘膜を保護。
②ハーブティー(カモミール・ルイボスなど)
カフェインを含まず、喉への刺激も少なく、リラックス効果も。
③ショウガ湯・はちみつ湯(ぬるめ)
殺菌・抗炎症・保湿効果が期待できる自然療法的な飲み方。
※ただし、個人差があるため体調や体質に応じて選びましょう。
喉に優しい食事とは?
摂りたい食品・避けたい食品とその工夫
⬛ 摂りたい食品
・大根+はちみつ
大根に含まれるアリルイソチオシアネートは抗炎症作用があり、はちみつは保湿・殺菌効果が期待できます。
・オリーブオイル
粘膜を保護する油分として活用可能。喉をコーティングし乾燥防止に。
・梨
含有されるサポニンが炎症を抑え、ミネラルで喉の潤いもサポート。ビタミンCを含む果物(適量) 粘膜の回復や免疫力維持に役立ちます。
⬛ 注意が必要な食品
・辛いもの
刺激が強く、粘膜を傷つける可能性あり。食べる場合は油分を含む食材と一緒に摂取するのが望ましい。
・糖分の多いもの(飴・菓子類)
ベタつき・痰の原因になることもあるが、膜を張って保護する作用も。過剰摂取に注意。
・乳製品
痰が絡みやすくなる場合があるが、体質によって問題のない人も。自己観察が重要。
喉を整えるための生活習慣とは?
声の調子を整えるには、飲食だけでなく、以下のような習慣の見直しも有効です。
・起床後や発声前はうがい・水分補給を習慣化
・部屋の湿度を50〜60%に保つ(加湿器・濡れタオルなど)
・口呼吸ではなく鼻呼吸を意識する(乾燥・異物侵入の防止)
・歌唱直前に激しい運動や辛いものを避ける
喉のケアを継続するために大切なこと
日々の食事や飲み物は、声の出やすさ・安定性・疲れにくさに直接影響します。「絶対に○○をしてはいけない」という極端な考えではなく、「目的に応じた摂取とコントロール」を意識することが大切です。
例えば、本番前・練習中・リラックス時で飲食内容を調整するなど、状況に応じた判断ができると理想的です。
まとめ:良い声は、良い習慣から
美しい声を支えるのは、日々の丁寧なケアと積み重ねです。
過度な練習よりも、喉の状態を整え、守る習慣こそが安定した歌声の基盤となります。
食べ方、飲み方、過ごし方を見直すことで、「声が出やすい」「疲れにくい」などの変化を感じるはずです。
本番前だけでなく、日常的に体調管理の一環として喉をいたわることは、音楽活動の質を高め、長く続けていくための大切な習慣です。
今日からできることから、少しずつ始めてみましょう。
当教室主宰の著書「音楽教育のススメ(幻冬舎)」